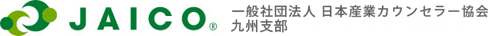ハラスメント相談窓口設置が義務化|パワハラやセクハラへの対応
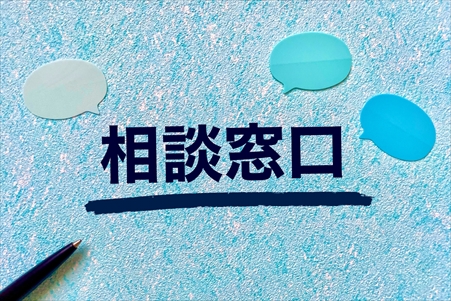
2020年6月、大企業向けに施行された改正労働施策総合推進法により、ハラスメント相談窓口の設置を含む防止措置が義務化されました。
その後、2022年4月から中小企業を含むすべての企業に適用が拡大され、企業規模を問わずすべての事業主が、職場におけるハラスメント対策を講じる必要があります。
本記事では、ハラスメント相談窓口義務化の背景や企業が対応すべきポイント、さまざまなハラスメントの種類について詳しく解説します。人事担当者や管理職の方が押さえておくべき実務的な内容をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
また、本記事はハラスメント相談窓口の設置に必要な知識を網羅的に解説していますので、1万文字を超えるボリュームとなっています。
お時間が無い方、対策のポイントだけ抑えておきたい方は、資料ダウンロードをお申し込みください。
お申し込み後、すぐにダウンロードいただけます。
本記事でわかること
- ハラスメント相談窓口の義務化の背景と法律の要点
- 企業が具体的に講じるべきハラスメント対策
- パワハラ、セクハラ、マタハラなど多様なハラスメントの種類と定義
- 実効性のある相談窓口の運営方法と外部専門機関を活用する有効性
- (一社)日本産業カウンセラー協会のハラスメント相談窓口について
目次
なぜハラスメント対策が重要なのか
職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながったりと、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題となっています。相談件数も年々増加しており、対策は喫緊の課題となっています。
ハラスメントの現状(データで見る実態)
厚生労働省の調査(2020年)によると、職場におけるハラスメントが深刻な問題となっている実態が確認できます。
| 調査項目 | 結果 |
|---|---|
| 過去3年以内にパワハラを受けた経験 | 31.4% |
| パワハラ相談件数(2020年6月以降) | 約1万8千件 |
| いじめ・嫌がらせ相談件数(2020年度) | 約8万件 |
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」(2020年)
ハラスメント相談窓口義務化の背景

パワハラ防止法の成立と経緯
2019年の第198回通常国会において「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、これにより労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。
大企業では2020年6月から施行され、中小企業においても2022年4月から義務化されました。これにより、企業規模を問わず、すべての事業主がハラスメント対策に取り組むことが法的に求められるようになったのです。
法改正による規制強化
併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正されました。
今までの職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られています。
現在の職場におけるハラスメントの実態
近年、ハラスメントに関する相談件数は増加傾向にあります。その内容も多様化しており、特にリモートワークの普及により、以下のような新たな形態のハラスメントが発生していることも注目すべき点です。
- オンラインでのコミュニケーションにおける配慮不足
- 過度な監視
- プライベート空間への無断侵入
また、ハラスメントを受けた労働者の多くが「相談しても無駄だと思った」「相談したことで不利益を被ることが心配だった」という理由で相談をためらう傾向があります。この点からも、安心して相談できる窓口の整備が急務となっているのです。
職場におけるパワーハラスメントの定義
労働施策総合推進法第30条の2において、職場におけるパワーハラスメントは以下のように定義されています。職場において行われる以下の①から③までの3つの要素をすべて満たすものをいいます。
- ①優越的な関係を背景とした言動であって
- ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- ③労働者の就業環境が害されるもの
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
「職場」とは
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
- 通常の就業場所
- 出張先
- 取引先
- 勤務時間外の懇親の場(実質上職務の延長と考えられる場合)
- 社員寮(実質上職務の延長と考えられる場合)
- 通勤中(実質上職務の延長と考えられる場合)
「労働者」とは
正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用するすべての労働者をいいます。
- 正規雇用労働者
- パートタイム労働者
- 契約社員
- その他非正規雇用労働者
- 派遣労働者(派遣元・派遣先双方が措置を講じる必要あり)
企業が知っておくべきハラスメントの種類

企業は多様なハラスメントに対応する必要があります。ここでは、職場で発生する可能性のある主なハラスメントの種類を詳しく解説します。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワハラは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものと定義されています。
厚生労働省の指針では、代表的な言動の類型として以下の6類型が示されています。
⑴ 身体的な攻撃(暴行・傷害)
| 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
| × 殴打、足蹴りを行う | 〇 誤ってぶつかる |
| × 相手に物を投げつける |
⑵ 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
| 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
| × 人格を否定するような言動を行う(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む) | 〇 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする |
| × 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う | 〇 企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする |
| × 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う | |
| × 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を複数の労働者宛てに送信する |
⑶ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
| 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
| × 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり別室に隔離したり、自宅研修させたりする | 〇 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する |
| × 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる | 〇 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために一時的に別室で必要な研修を受けさせる |
⑷ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
| 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
| × 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる | 〇 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる |
| × 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する | 〇 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる |
| × 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる |
⑸ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
| 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
| × 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる | 〇 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する |
| × 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない |
⑹ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
| 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
| × 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする | 〇 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う |
| × 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する | 〇 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す |
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクハラは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることを指します。
セクハラの2類型
| 類型 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 対価型 | 性的な言動への対応により不利益を受ける | 性的な関係を要求して拒否されたため解雇・降格する |
| 環境型 | 性的な言動により就業環境が害される | 身体への接触、性的な冗談、執拗なデートへの誘い |
【重要ポイント】
- 行為者は上司や同僚だけでなく、取引先や顧客なども含まれる
- 異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当
- 被害者の性的指向や性自認にかかわらず成立
マタニティハラスメント(マタハラ)
マタハラは、妊娠・出産・育児休業などに関する制度の利用を理由とした不利益な取扱いや、嫌がらせを指します。
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。
制度等の利用への嫌がらせ型
- 産前休業の取得を相談したら「休みを取るなら辞めてもらう」と言われた
- 育児休業について相談したら「男のくせに取るなんてあり得ない」と言われた
- 時間外労働の免除について相談したら「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた
状態への嫌がらせ型
- 妊娠を報告したら「早めに辞めてもらうしかない」と言われた
- 「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し言われた
- 「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と継続的に言われた
その他のハラスメント
上記以外にも多様なハラスメントが存在します。企業はこれら広範なハラスメントに対しても予防・対応措置を講じる必要があります。
| ハラスメント | 略称 | 内容 |
|---|---|---|
| カスタマーハラスメント | カスハラ | 顧客からの著しい迷惑行為(長時間クレーム、土下座要求、暴言など) |
| モラルハラスメント | モラハラ | 言葉や態度による継続的な人格否定、陰口、無視など |
| リモートハラスメント | リモハラ | Web会議中の部屋の詮索、プライベート時間帯の業務連絡、常時カメラオン強要など |
| アルコールハラスメント | アルハラ | 飲酒の強要や一気飲みの強制 |
| スモークハラスメント | スモハラ | 喫煙者が非喫煙者に与える迷惑行為 |
| ジェンダーハラスメント | - | 性別に基づく固定観念による嫌がらせ |
| エイジハラスメント | - | 年齢を理由とした差別的言動 |
| テクノロジーハラスメント | テクハラ | ITスキルの差を利用した嫌がらせ |
| ケアハラスメント | - | 介護を理由とした不利益取扱い |
事業主が雇用管理上講ずべき措置
労働施策総合推進法第30条の2では、事業主は以下の4つの柱からなる措置を講じなければならないと定めています。

1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
ハラスメントの内容及び行ってはならない旨の方針の明確化
就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景等を労働者に周知・啓発することが必要です。
【周知の方法】
- 社内報
- パンフレット
- 社内ホームページ
- 広報又は啓発のための資料等
また、職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施することも重要です。
行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に、ハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発することが必要です。
対処の内容を文書に規定することは、ハラスメントに該当する言動をした場合に具体的にどのような対処がなされるのかをルールとして明確化し、労働者に認識してもらうことによって、ハラスメントの防止を図ることを目的としています。
【懲戒処分の例】
- 戒告
- 減給
- 出勤停止
- 降職
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
- 譴責
2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口の設置
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること、相談に対応するための制度を設けること、外部の機関に相談への対応を委託することなど、窓口を形式的に設けるだけでは足りず、実質的な対応が可能な窓口が設けられていることが必要です。
【相談方法の例】
- 電話
- メール
- 対面
- Web会議
相談に対する適切な対応
相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすることが重要です。
また、相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること、相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うことも必要です。
相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応することが求められます。
3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
事実関係の迅速かつ正確な確認
相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること、その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも適切に配慮することが必要です。
また、相談者と行為者の間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずることが求められます。
被害者に対する適正な配慮の措置
事案の内容や状況に応じ、以下の措置を講ずることが必要です。
- 被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
- 被害者と行為者を引き離すための配置転換
- 行為者の謝罪
- 被害者の労働条件上の不利益の回復
- 管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等
行為者に対する適正な措置
就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずることが必要です。
併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措置を講ずることも重要です。
再発防止措置の実施
職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の事業主の方針及び職場におけるハラスメントに係る言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配付等すること、労働者に対して職場におけるハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施することが必要です。
4. 併せて講ずべき措置
プライバシー保護
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知することが必要です。相談者や行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれます。
不利益取扱いの禁止
事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発することが必要です。
中小企業における対応のポイント

中小企業では人事部門が存在しない、または限られた人員で運営している場合が多く、相談窓口の設置が課題となります。しかし、企業規模にかかわらず義務は同じです。中小企業では、外部リソースの積極的な活用など、効率的かつ実効的な対応が求められます。
中小企業の定義
労働施策総合推進法における中小企業の定義は以下の通りです。
| 業種 | 資本金または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
効果的な対応策
複数の相談ルートの確保
社内窓口だけでなく、外部の専門機関を活用することで、相談のハードルを下げることができます。
経営者の明確なメッセージ
トップ自らがハラスメント防止の重要性を発信することで、組織全体の意識が変わります。
外部リソースの活用
産業カウンセラーや社会保険労務士など、外部の専門家の力を借りることで、専門性の高い対応が可能になります。人事リソースが限られている企業にとって、外部専門家は実効性の高いハラスメント対策を可能にする重要な選択肢です。
違反した場合のリスク
ハラスメント対策を怠った場合、企業には以下のような重大なリスクが発生します。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 行政指導と企業名公表 | 厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象。勧告に従わない場合は企業名が公表される |
| 損害賠償責任 | 安全配慮義務違反として、 数百万円〜数千万円 の賠償を命じられる可能性 |
| 人材採用への悪影響 | 優秀な人材の確保が困難に。特に若い世代は職場環境を重視。 |
| 生産性の低下 | 従業員のモチベーション低下、離職率上昇により企業の競争力が低下 |
効果的なハラスメント相談窓口の運営方法

相談窓口を形式的に設置するだけでは不十分です。実効性のある運営のためには、従業員が安心して利用できる環境づくりが欠かせません。
相談しやすい環境づくり
匿名相談の受付
実名での相談に抵抗がある従業員も多いため、匿名での相談も受け付ける体制を整えることが重要です。匿名相談であっても、状況によっては適切な対応を取ることができます。
複数の相談チャネルの用意
電話、メール、対面、Web会議など、複数の相談方法を用意することで、相談者が最も利用しやすい方法を選択できます。特にメールやWebフォームは、緊急性が低い相談や、対面では話しにくい内容の相談に適しています。
社外窓口の設置
社内の人間には相談しにくいという心理的ハードルを下げるため、外部の専門機関に相談窓口を委託することも有効です。第三者の客観的な視点は、問題の早期発見と適切な対応につながります。日本産業カウンセラー協会でもハラスメント相談窓口サービスを提供しておりますので、ハラスメント相談窓口の設置や、外部委託をご検討中の企業様は資料ダウンロードをお申し込みください。お申し込み後、すぐにダウンロードいただけます。
相談窓口担当者の育成
相談対応には高度なスキルが必要です。厚生労働省の指針でも、相談窓口担当者に対する研修の実施が推奨されています。
【必要なスキル】
| スキル | 内容 |
|---|---|
| 法律知識 | 関連法令や企業の責任範囲についての理解 |
| 傾聴スキル | 相談者の話を丁寧に聴き、心情を理解する技術 |
| 中立性の維持 | 先入観を持たず、公平な立場で事実関係を確認 |
| 守秘義務の徹底 | 相談内容の取り扱いに関する厳格なルールの遵守 |
| 二次被害の防止 | 不適切な対応により相談者をさらに傷つけないよう注意 |
ポイント:ハラスメントを受けた心理的影響から理路整然と話すことができない場合がありますので、 忍耐強く傾聴に努める ことが重要です。
相談を受けた後の対応フロー

相談を受けた後の適切な対応手順を確立しておくことが、事態の悪化を防ぎ、企業の責任を果たす上で重要です。
1.初期対応(相談受付)
相談者の話を丁寧に傾聴し、状況を把握します。この段階では判断を急がず、まず相談者の気持ちを受け止めることが大切です。相談を受ける場所や時間帯等も、相談者が安心して相談できる状況となるよう工夫しましょう。
2.事実関係の確認
関係者からのヒアリングを行い、客観的な事実を確認します。相談者、行為者双方の言い分を公平に聴取し、第三者の証言も集めます。この際、プライバシーへの配慮が不可欠です。
相談者と行為者の間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずることが必要です。
3.対応方針の決定
事実関係に基づき、ハラスメントに該当するか判断し、対応方針を決定します。必要に応じて弁護士などの専門家の意見も参考にします。
4.措置の実施
被害者への配慮措置(配置転換、休職措置など)と、行為者への措置(懲戒処分、配置転換、研修など)を実施します。措置の内容は、事案の重大性に応じて適切に判断する必要があります。
5.再発防止策の実施
同様の問題が再発しないよう、職場環境の改善や研修の実施など、具体的な再発防止策を講じます。
6.フォローアップ
措置実施後も、被害者の状況を継続的にフォローし、問題が解決されたか確認します。相談担当者が相談を受けて終わりなのではなく、事業主としてどのように判断したのか、今後組織としてどのように対応していくのか等を相談者本人にフィードバックすることも大切です。
7.記録の保管と活用
相談内容や対応経緯は適切に記録し、保管する必要があります。記録は以下の目的で活用されます。
- 対応の適切性の検証
- 類似事案発生時の参考資料
- 法的紛争が生じた際の証拠
- ハラスメント傾向の分析と予防策の立案
ただし、記録の保管にあたってはプライバシー保護に十分配慮し、アクセス権限を厳格に管理する必要があります。
ハラスメント予防のための取り組み

相談窓口の設置と並行して、ハラスメントを未然に防ぐための取り組みも重要です。
研修・教育の実施
管理職向け研修
管理職は部下のマネジメントにおいてハラスメントのリスクが高い立場にあります。適切な指導とハラスメントの境界線、部下との適切なコミュニケーション方法などを学ぶ研修が必要です。
定期的に実施する、調査を行うなど職場の実態を踏まえて実施する、管理職層を中心に職階別に分けて実施するなどの方法が効果的と考えられます。
全従業員向け研修
すべての従業員がハラスメントについての正しい知識を持つことが重要です。どのような行為がハラスメントに該当するのか、ハラスメントを見かけたらどうすべきか、といった基本的な内容を定期的に教育します。
新入社員研修
入社時からハラスメント防止の意識を持つことは、健全な職場文化の形成に役立ちます。企業の方針や相談窓口の存在を早期に伝えることが大切です。
その他の予防策
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 就業規則の整備 | ハラスメントの禁止を就業規則に明記し、懲戒処分の内容を明確化(戒告〜懲戒解雇まで) |
| コミュニケーション活性化 | 1on1ミーティング、チームビルディング、オープンな組織風土の醸成 |
| アンケート調査 | 定期的に従業員アンケートを実施し、職場環境の実態を把握。 |
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置を講ずることも事業主の義務となっています。
ハラスメント発生の原因・背景
ハラスメント発生の原因・背景として、主に以下の2点が挙げられます。
| 原因 | 背景 |
|---|---|
| 職場風土 | 妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動が頻繁に行われることや、制度等の利用や請求をしにくい職場風土であること。 |
| 周知不足 | 制度等の利用ができることについて、職場内での周知が不十分であること。 |
【否定的な言動の例】
否定的な言動は、制度等の利用を検討している本人に直接行われない場合も、ハラスメントの原因や背景になり得ます。
- 夫婦が同じ会社に勤務している場合。
- 育児休業を取得する本人ではなく、その配偶者に対して否定的な言動を行う行為。
原因・背景を解消するための対策
以下の対策を通じて、制度等の利用や請求をしやすくするような工夫をし、全従業員の理解を深めることが大切です。
- 利用する本人だけでなく、全従業員に制度等への理解を深めてもらうための理解促進。
- 事業主や妊娠等した労働者、その他の労働者の実情に応じた業務体制の整備を行う。
関係者の責務
2019年の法改正により、職場におけるハラスメントの防止のために、事業主や労働者に対して、主に以下の事項について努めることとする責務規定が定められました。
事業主の責務
- 職場におけるハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるハラスメントに起因する問題に対する自社の労働者の関心と理解を深めること
- 自社の労働者が他の労働者(取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含む)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その他の必要な配慮をすること
- 事業主自身(法人の場合はその役員)が、ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
労働者の責務
- ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、他の労働者(取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含む)に対する言動に必要な注意を払うこと
- 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
職場におけるハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、行ってはならない行為です。事業主及び労働者は、ハラスメントの防止のための自らの責務をしっかりと認識しつつ、ハラスメントのない職場をつくっていきましょう。
ハラスメント相談窓口に関するよくある質問(Q&A)
Q1. ハラスメント相談窓口の設置は、どの企業に義務化されていますか?
A. 2022年4月から、企業規模を問わずすべての企業に義務化されています。
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から相談窓口の設置が義務付けられました。
義務化の対象は相談窓口の設置だけでなく、方針の明確化・周知啓発、事後対応、プライバシー保護なども含まれます。違反した場合は行政指導の対象となり、企業名が公表される可能性もあります。
Q2. パワハラとセクハラの違いは何ですか?
A. パワハラは「優越的な関係を背景とした言動」、セクハラは「性的な言動」による嫌がらせです。
| 項目 | パワハラ | セクハラ |
|---|---|---|
| 定義 | 優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で就業環境を害する | 労働者の意に反する性的な言動により不利益を受ける、または就業環境が害される |
| 法的根拠 | 労働施策総合推進法 | 男女雇用機会均等法 |
パワハラには身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離しなど6類型があります。セクハラは対価型(拒否による不利益)と環境型(就業環境の悪化)に分類されます。
Q3. ハラスメント相談窓口は社内設置と外部委託、どちらが良いですか?
A. それぞれにメリットがあり、併用が最も効果的です。
| 設置形態 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 社内窓口 | 迅速な対応、コスト抑制 | 相談しにくい、中立性の確保が課題 |
| 外部委託 | 中立性・専門性が高い、安心感 | コスト発生、社内事情の把握に時間 |
Q4. 相談したことで、不利益を受けることはありますか?
A. 法律で不利益取扱いは明確に禁止されています。
労働施策総合推進法等により、ハラスメントについて相談したことや事実確認に協力したことを理由とする解雇、降格、減給などの不利益取扱いは禁止されています。
事業主は、不利益取扱いを行わない旨を就業規則等に明記し、全従業員に周知することが義務付けられています。外部の相談窓口を利用すれば、より安心して相談できます。
Q5. 相談窓口の担当者には、どのようなスキルが必要ですか?
A. 傾聴スキル、法律知識、中立性の維持、守秘義務の徹底が求められます。
| スキル | ポイント |
|---|---|
| 傾聴スキル | 被害者は理路整然と話せないことも多いため、忍耐強く聴く |
| 法律知識 | 関連法令や企業の責任範囲を理解する |
| 中立性 | 先入観を持たず、双方から公平に事実確認を行う |
| 守秘義務 | 相談内容や機微な個人情報を適切に保護する |
社内での担当者育成が難しい場合は、外部専門家への委託も有効です。
(一社)日本産業カウンセラー協会のハラスメント相談窓口

ハラスメント対策において、外部の専門機関を活用することは非常に有効です。一般社団法人日本産業カウンセラー協会は、企業のハラスメント相談窓口として高い専門性を持つサービスを提供しています。
協会の特徴と専門性
一般社団法人日本産業カウンセラー協会は、1960年の設立以来、60年以上にわたり産業カウンセリングの分野で活動してきた実績のある団体です。全国に約36,000名の産業カウンセラーが所属し、働く人々のメンタルヘルスとキャリア形成を支援しています。
産業カウンセラーは、心理学の知識と企業組織への理解を併せ持つ専門家です。国家資格であるキャリアコンサルタントや、臨床心理士などの資格を併せ持つカウンセラーも多く、ストレスチェックの実施も支援するなど、高度な専門性を有しています。
ハラスメント相談窓口サービスの内容
一般社団法人日本産業カウンセラー協会が提供するハラスメント相談窓口サービスには、以下のような特徴があります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 専門的な相談対応 | ハラスメント問題に精通した産業カウンセラーが、心理的なケアから実務的な助言まで、丁寧に傾聴し、相談者をサポートします。 |
| 中立的な立場 | 外部機関であることから、社内の人間関係に左右されない中立的な立場で相談に応じることができます。 |
| 守秘義務の徹底 | カウンセラーは厳格な守秘義務を負っておりますので、相談内容や個人情報が第三者に漏れることが無いよう、適切に保護します。 |
| 柔軟な相談方法 | 電話、メール、オンラインなど、複数の相談方法に対応しており、相談者の都合に合わせて利用できます。 |
| ワンストップのサポート | 相談窓口だけでなく研修やコンサルまで、様々な業種・規模の企業に対応したサポートができます。 |
資料ダウンロード
ハラスメント相談窓口の設置や、外部委託をご検討中の企業様向けに、お役立ち資料を用意しました。
ハラスメント対策の情報収集をされている方や、一般社団法人日本産業カウンセラー協会のサービス内容を詳しく知りたい方は、資料をご確認ください。
お申し込み後、すぐにダウンロードいただけます。
まとめ
ハラスメント相談窓口の設置義務化は、すべての企業が対応すべき重要な課題です。適切な体制を整備することで、従業員が安心して働ける職場環境を実現し、企業の持続的な成長につなげることができます。
本記事で解説したように、事業主には以下の措置を講じることが法律で義務付けられています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
これらの措置を適切に実施することで、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止し、万が一発生した場合にも適切に対応することができます。
ハラスメント対策は、コンプライアンスの観点だけでなく、優秀な人材の確保、生産性の向上、企業ブランドの向上といった経営上のメリットももたらします。
ハラスメント相談窓口の設置にあたっては、社内のリソースだけで対応しようとせず、一般社団法人日本産業カウンセラー協会のような外部の専門機関を活用することも有効な選択肢です。専門家の力を借りることで、より実効性の高いハラスメント対策が可能になります。
参考文献
- 厚生労働省「パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されます」
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
この記事の執筆者

鈴木 勇太
1988年生まれ。福岡医療福祉大学人間社会福祉学部臨床医療福祉学科卒業。2010年に産業カウンセラー、2015年にキャリアコンサルタント取得。一般社団法人日本産業カウンセラー協会広報・広告部長。
この記事の監修者

木村 潤
1960年生まれ。宮崎大学大学院工学研究科工業化学専攻修了。一般社団法人日本産業カウンセラー協会九州支部支部長。